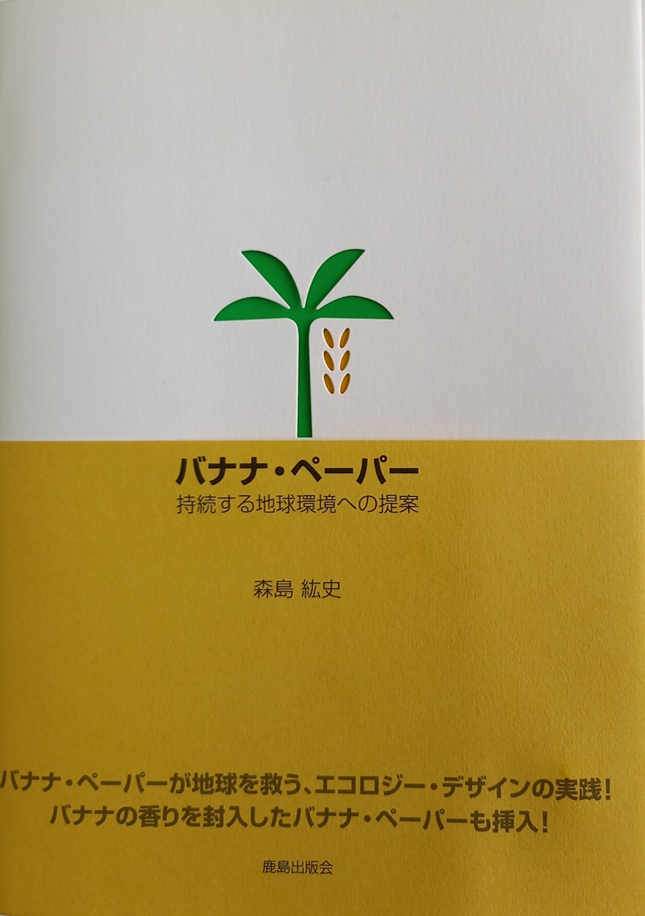《バナナ・ペーパーの足跡を追って…》(その2)
【今回、出会った本】
『バナナ・ペーパー 持続する地球環境への提案』
森島紘史著 (鹿島出版会)2005年8月
バナナは日本の家庭ではもはやきわめて馴染み深い果物として定着している感じがする。歳がばれるのであまり話したくはないのだが、私が小学低学年だった頃は、事情は現在とはいささか異なっていて、バナナが食べられるのは遠足か運動会のときと決まっていた。みかんやリンゴなどと違い、バナナは今よりもずっと高級品だったような印象がある。そのあたりの歴史をグーグルで調べてみると、その時分のバナナは台湾産のいわゆる「台湾バナナ」で、文字通り高級品だったらしい。1972年の日本・台湾間の国交断絶以後、輸入量は減少してしまったという。ちなみに、現在、スーパーやコンビニなどでみかけるバナナは圧倒的にフィリピン産のものが多いようだ。
そんな身近なバナナだが、実はその植生については一般にはそれほど広く知られているとは言いがたい。だいたいバナナにはそのまま食べられる生食用「バナナ」と、煮たり揚げたりしなければ食べられない料理用の「プランテン」の二種類がある。そんな基本的なことすら、私はこの歳になるまで知らないできた。お恥ずかしいかぎりである。また「バナナ」という名前の語源だが、アラビア語の「指先(Banan)」に由来するという説と西アフリカ語の「(複数の)指(Banema)」に由来するという説と二通りあるようだ。どちらの説もあってるようであってないような微妙な感じだが、いずれも〝手〟に関係した言葉である点が面白い。たしかにバナナの房の形状は人の手を連想させるし、その感じかたは万国共通なのだろう。
ところで、私がこの本『バナナ・ペーパー 持続する地球環境への提案』を取りあげた理由は、その内容がバナナを新しい非木材資源として多角的に紹介する内ものだったことにある。著者の森島氏は、バナナのそうした利用側面についてはどのように書かれているだろうか。
以下に、バナナの資源活用にむけた基本的な観点について述べられた箇所を引用する。
(ここから引用)
バナナは実を収穫する際、巨大な茎(仮茎・葉鞘)と葉は、切り倒されてその場に捨てられている。それには2つの理由がある。ひとつは、手を伸ばしてやっと届くほど高い位置に実(約15~20キログラム)が下がるため、根元で茎を切ることで手許に引き寄せ、実を傷つけずに収穫するためであり、他のひとつは、バナナは一度実がなれば枯れるので茎を切ることで栄養分を新芽にまわすためである。
(中略)このようにバナナ農業では、収穫時に果実の5~10倍の重量がある茎と葉(仮茎・葉鞘・葉身)が農産廃棄物として派生して、ゴミとしてその場に捨てられている。これが、本プロジェクトの主役となる天然資源である。(18~19頁)
(引用ここまで)
なるほど、ここに書いてあることは果たして私が三十年ほど前に御田先生から聞いた内容とまったく同じである。状況は三十年前となにも変わってはいないらしい。ただ、バナナの茎が切り倒される理由のひとつが、「栄養分を新芽にまわすため」だという事実は初めて知ったような次第である。こうした自然の世代循環の輪が、バナナ栽培の輪のなかでも活かされている姿は、現場を知らない私たちにとっては想像すらできなかった知見であろう。
であるならば、バナナ茎の具体的な形状はいったいどのようなものなのだろうか。
(ここから引用)
さて、捨てられている茎を輪切りにして見ると三日月を丸めた形状の鞘(シース)が抱き合うように10枚前後重なり、鞘の中では格子状に小さな隙間が並び、中には空気や水が入っている。バナナの繊維組織は、この鞘の外側にあたる壁の部分に多く発達し、中心にある花(果)軸に近いほど、繊維が白く細くなっている。従って、太く強靭な繊維は外側の茎から、細く繊細な繊維は内側の茎から採取することができる。中心の花軸にも繊維はあるが、極細の蜘蛛と糸のような繊維の集合体であり、採取するのは容易ではない。(19頁)
(引用ここまで)
じつは昨年の夏に、筆者はたまたま取り寄せることのできたバナナ茎を、研究のために解体した経験がある。それは、まったくここに記されているとおりの形状だった。そんなことがあったので、私じしんは引用部に書かれてある内容はとてもよく理解できるのだが、まだそれを一度も見たことのない人であれば、一読しただけではなかなかその具体像を思い浮かべるのが難しいのではないかと懸念する。手持ちの写真を何枚か貼りつけるのでご参考にしていただければ幸いである。
ここに書かれていないことで特に注記することがあるとすれば、水分含有率が高いので持ちあげるとズシンと腰にくることや、組織をバラバラにしていく過程でどこかしら甘たるいバナナらしい香りが最後まで漂ったことである。(続く)